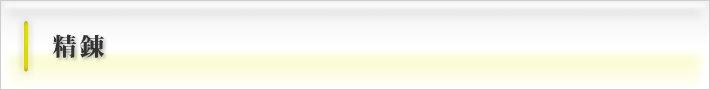繭糸は繊維であるフィブロインをセリシンが覆っているという構造になっています。着色繭、特にカロチノイド系の色素を含んでいる繭は、セリシンに多くの色素を含んでいます。セリシンは熱水やアルカリに溶ける特性なので実際に溶かしてみました。

(1) 5gの繭を細かく切ります。

(2) 切ったものをガーゼにくるみます。

(3) 500gの水にマルセル石鹸1gと炭酸ソーダ(炭酸ナトリウム)0.25gを入れ沸騰させます。炭酸ソーダが無い場合は重曹を0.5g入れます。

(4) (2)を(3)に入れ40分煮ます。反応を早くさせるためにガラス棒などで突きます。

(5) 40分煮るとオレンジジュースみたいになります。
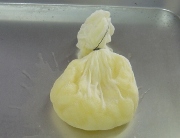
(6) 40分後繭を取り出しよく絞ります。

(7) 新しく作った(3)に(6)を入れまた40分煮ます。 二回目はあまり色が出ません。

(8) 40分後、水でよく洗って乾燥させたものです。だいぶ白くなりました。
繭は基本的に年4回、春・夏・初秋・晩秋に収穫されます。夏と秋は桑に付いた野外昆虫の影響や、気象条件によって蚕が病気になりやすく、昭和初期まで作柄が不安定でした。作柄を安定させるために品種改良が進み、昭和中期から質の良い糸がとれ、病気に強い品種の蚕が飼育されるようになりました。品種改良により、現在は明治時代と比べて飼育日数が約67%に減少し、一粒の繭の重さが約1.8倍になり、一粒の繭からとれる糸の長さが約2.2倍になりました。
年々繭の生産量は減少していますが、特徴のある糸がとれる繭は注目されています。特に細い糸がとれる品種の需要が増えています。細い絹糸は光沢が強く軽いので高級品に利用されています。